📝 目次
- 【はじめに】認知症と「できなくなることへの不安」
- 便利な調理器具・電子レンジに見えた「不便」
- ワット数や時間の細かい設定が難しい
- サニーちゃんの驚くべき「工夫」
- なぜ見えにくいのか?高齢者の視界と色彩
- 母の訴え「文字が小さくて見えにくい」
- 高齢者の視界は「褐色のサングラス」のよう
- いま自分が便利なものが、将来も便利とは限らない
- 【おわりに】優しい社会へ。小さな不便を教えてください
1. 【はじめに】認知症と「できなくなることへの不安」
みなさんは、日々学んで知識を獲得したり、それらを忘れずに暮らしに役立てることができていらっしゃるのと思います。少なくとも、忘れる事柄と覚えた事柄が同じくらいある、という状態ではないでしょうか?
しかし、認知症は、忘れる事柄が次々に増えていったり、覚えたことを保持できなくなるのが症状の一つです。
そして、忘れたり、できなくなることが増えていくと、本人も不安になったり、気持ちも塞いでしまうようです。
1年を振り返ってみると、私の母であるサニーちゃんは、確実にできないことが増えました。
2. 便利な調理器具・電子レンジに見えた「不便」
ワット数や時間の細かい設定が難しい
ちょうど1年前、レンジで魚やお肉が焼ける便利な調理器具を買いました。
最初は「便利ですごいわぁ」と言っていたサニーちゃんですが、最近では、レンジのワット数を選んだり、○分○秒と細かい設定は難しくなってしまいました。
難しくなった原因は、主に次の二つです。
- デジタル表示が小さくて見えにくいこと
- どこを押せば時間を設定できるのかわからなくなってしまうこと
この時間設定ができないと、日々の食卓に欠かせない冷凍食品の調理もできません。
サニーちゃんの驚くべき「工夫」
ある日、「どうやってチンしてたの?」とサニーちゃんに聞いてみました。返ってきた答えに、私は感動しました。
「あっためボタンを押して、できあがりそうになったら止めてた」
つまり、サニーちゃんはレンジの前でじっと出来上がり具合を確認していたわけです。
「できない」と諦めるのではなく、本人なりに工夫して、なんとか生活を維持しようとしているその姿に「えらいなぁ」と心の中でサニーちゃんを抱きしめました。
母の訴え「文字が小さくて見えにくい」
サニーちゃん曰く、レンジの表示は小さくて見えにくいそうです。
「もっと大きな文字ではっきりと表示されれば見えるのに」
そう言いながら、サニーちゃんはレンジを使うときに、虫眼鏡を持ちながら時間設定しています。
確かに、言われてみれば、電子レンジの時間設定やワット数表示の部分は、それほど大きくない製品が多いです。ですが、私たちにとっては「当たり前の大きさ」で不自由に感じたことはありませんでした。
3. なぜ見えにくいのか?高齢者の視界と色彩
高齢者の視界は「褐色のサングラス」のよう
「年を取ったら目が悪くなっても仕方がない」と思い込み、サニーちゃんがどんな風に見えているのか、想像すらしなかった私の勉強不足のせいだと反省しています。
実は、高齢になると目の水晶体が黄色く濁ってしまい、ものをはっきり見分けにくくなるようです。例えるなら、褐色のサングラスをかけてものを見ているようなイメージ」だそうです。
黒い背景にグレーの文字、といったコントラストが弱い表示や、青や緑などの識別も難しくなるのだとか‥。
- (参考)高齢者の視覚について、詳しく書かれたホームページをシェアしますね。
前もって上記のような情報を見ていれば、電子レンジを買い換える時に、もっとコントラストがはっきりした、シンプルな表示の電子レンジを選んであげられたのになぁと、今さらながら悔やみました。また、世の中には音声ナビ付きの電子レンジもあるそうです。このブログを書いている時点で知りました。
4. いま自分が便利なものが、将来も便利とは限らない
私自身、サニーちゃんに言われるまで、電子レンジの表示部分に疑問を感じたことはありませんでした。タイマーや機能設定面よりも、庫内が見やすい物の方が料理をする際に便利とさえ思っています。
けれども、認知症のような障害を持った人には、不自由に感じる「便利用品」があるのだと気付かされました。
つまり、いま自分が便利に使っているモノでも、将来は不自由に感じる時が来るかもしれない、というわけです。
認知症の人の行動や考え方、モノの見え方など、まだまだ知られていないことが多いからでしょうか。
視覚的・身体的に不自由な人が使いやすく設計されたら、もっと優しい社会になるのではないでしょうか?
将来、自分が認知症になった時でも、できるだけ自分一人の力で生きていけるように、認知症の人目線の生活器具が世の中にもっと増えることを願っています。
5. 【おわりに】優しい社会へ。小さな不便を教えてください
私は、日常に隠れている「小さな不便」に、なかなか気づくことができませんでした。
みなさんの身の回りにある『当たり前の便利』の中に、もし気づいていない『小さな不便』があったら、ぜひコメントで教えてください。
一緒に優しい社会について考えていただけたら嬉しいです。
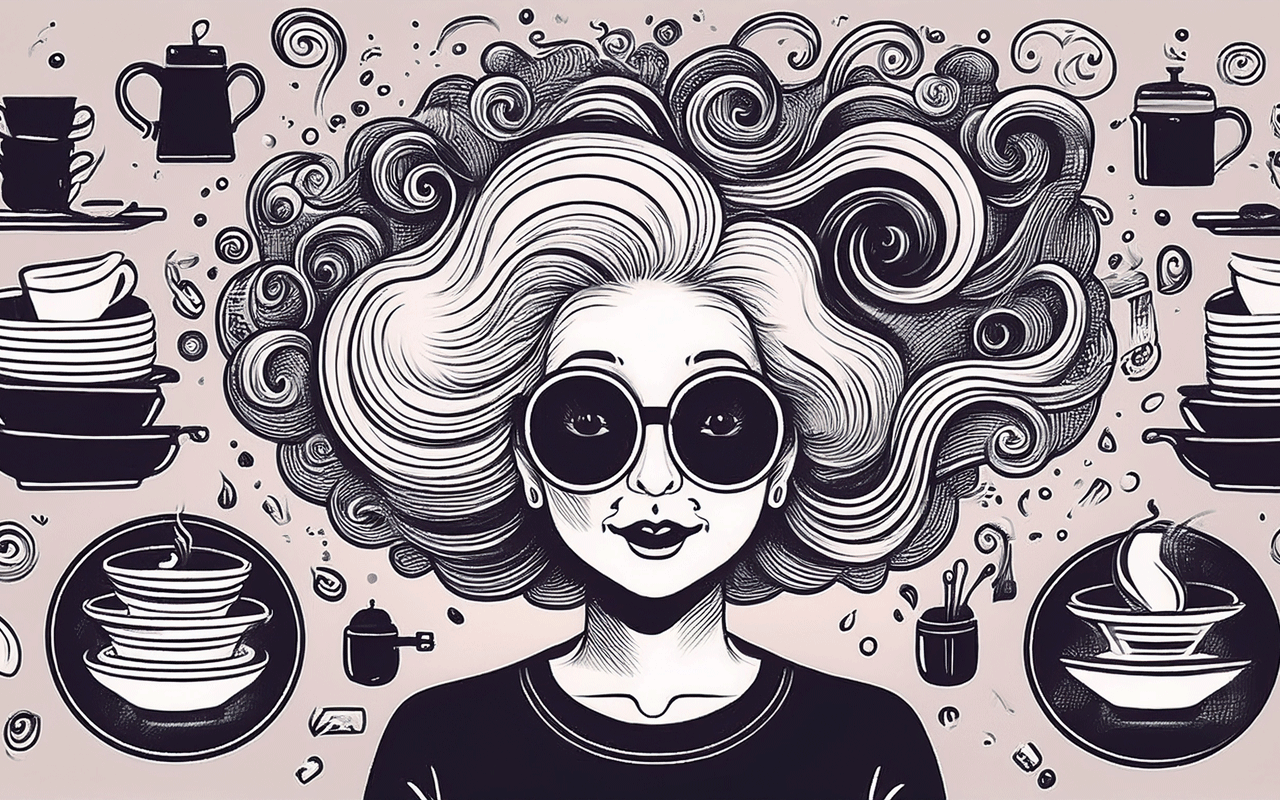
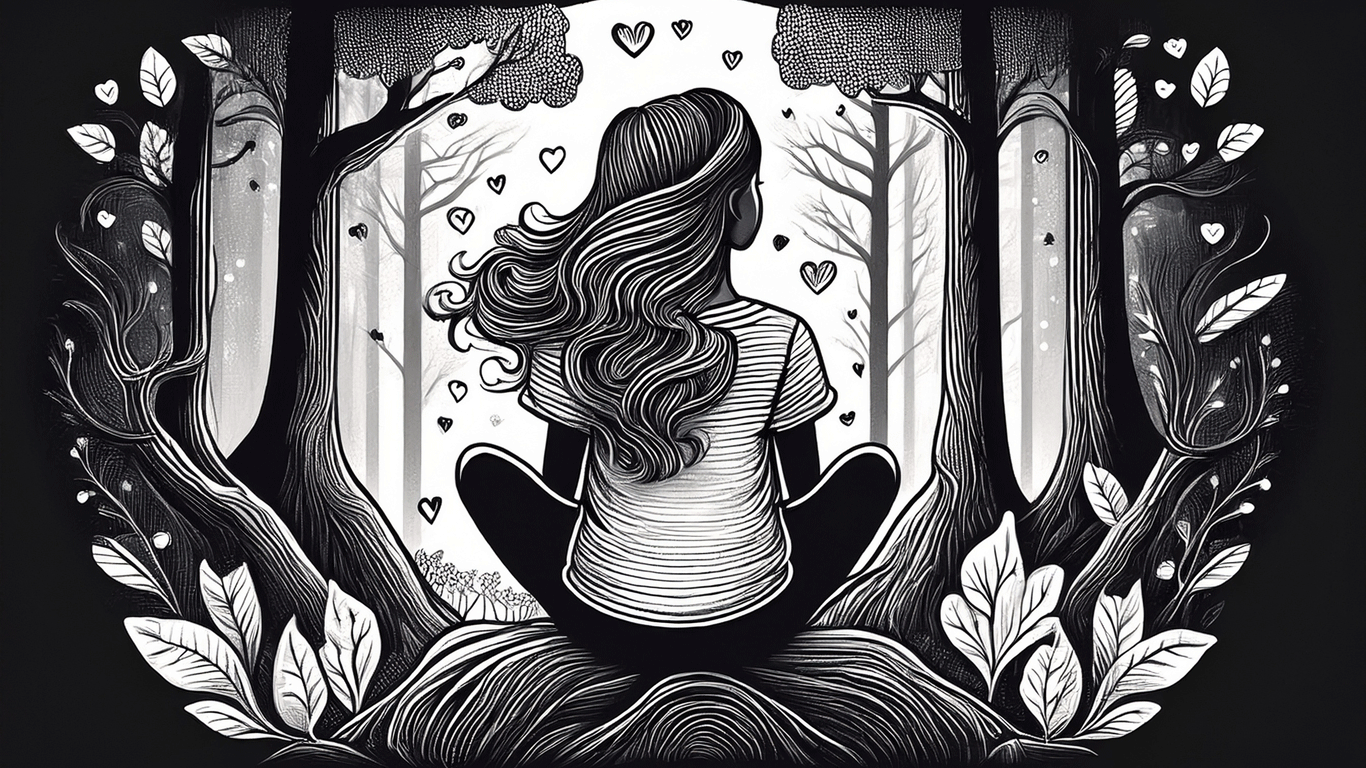
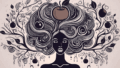
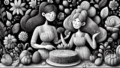
コメント