最近、私はサニーちゃん(母)に接する際、以前にも増して「笑顔で話す」ことを心がけるようになりました。そのきっかけとなったのは、認知症医療の第一人者である長谷川和夫先生の著書『ボクはやっと認知症の人のことがわかった』を読んだからです。
長谷川先生といえば、認知症診断の現場で広く使われている「長谷川式簡易知能評価スケール」を開発された、「認知症の専門家」としてあまりにも有名です。その先生が、ご自身が認知症と診断され、当事者として病気と向き合い、共に生きる道を見出していく過程を綴ったのが本書です。
「わからない」のではなく「反論できない」だけ
この本を読んで、最も心を揺さぶられたものの1つに、「認知症の人の前でその人を軽んじる話をしたら、深く傷つけることになる。ご本人は理解できないのではない、ただ反論できないだけなのだ」という内容でした。
この言葉は、私を過去に引き戻しました。子育て時代、ママ友同士で「うちの子昨日もまたさぁ…」と子どもの前で話していると、決まって子どもがぐずることがあったんです。「あれ?伝わってるのかな?」と疑問に思った経験がありましたが、やはり悪気はなくても、例え家族であっても本人を軽んじる話はしないほうがいいのだと改めて感じました。
「何をしたいですか?」そして「待つ時間」を差し上げる大切さ
また、本書では、認知症の人への接し方について具体的なヒントが与えられています。1例として私の印象に残ったものをあげますね。
- 「これをやりましょう」と提案するのではなく、「何がしたいですか?」と尋ね、同時に「何をしたくないのか」も聞いてほしい。
- そして何よりも大切なのは、尋ねたら答えが返ってくるのを「待ってほしい」ということ。
長谷川先生は、「返事に時間はかかるが、待つことが大切。その人に時間を差し上げてほしい」と述べています。この言葉は私の心に深く刻まれました。
これは目から鱗が落ちるような言葉でした。例えば、サニーちゃんとのやり取りの中で、彼女が話す内容を私が「要するに…」と遮ろうとした時、「そうやるから話せなくなっちゃうのよ!」と怒っていた姿が鮮明に蘇りました。
私たちはとかく効率を重視しがちですが、認知症の方にとっては、その「待つ時間」こそが、自分の意思を整理し、表現するために不可欠な時間だったのです。
笑顔と「待つ時間」が織りなすコミュニケーション
長谷川先生ご自身の経験に基づいたこれらの教えは、私とサニーちゃんのコミュニケーションを大きく変えるきっかけとなりました。
「分からない」と決めつけず、丁寧に耳を傾け、答えを「待つ時間」を差し上げる。そして、何よりも笑顔で接すること。
言葉を交わす際の私のわずかな表情や態度が、サニーちゃんの安心感につながり、それがコミュニケーションの円滑さに影響すると改めて実感しています。
長谷川先生の言葉には、当事者の経験があるからこその、ずっしりとした重みがあります。
私たち介護する側が認識を変えていけば、認知症の方々にとって、より住みやすい社会になるのではないでしょうか?そしてそれは、巡り巡って、私たち自身が将来安心して暮らせる社会へとつながると信じています。
本書は、認知症の方々と真に心を通わせるための、かけがえのない道しるべとなるでしょう。ぜひ多くの方に読んでいただきたい一冊です。
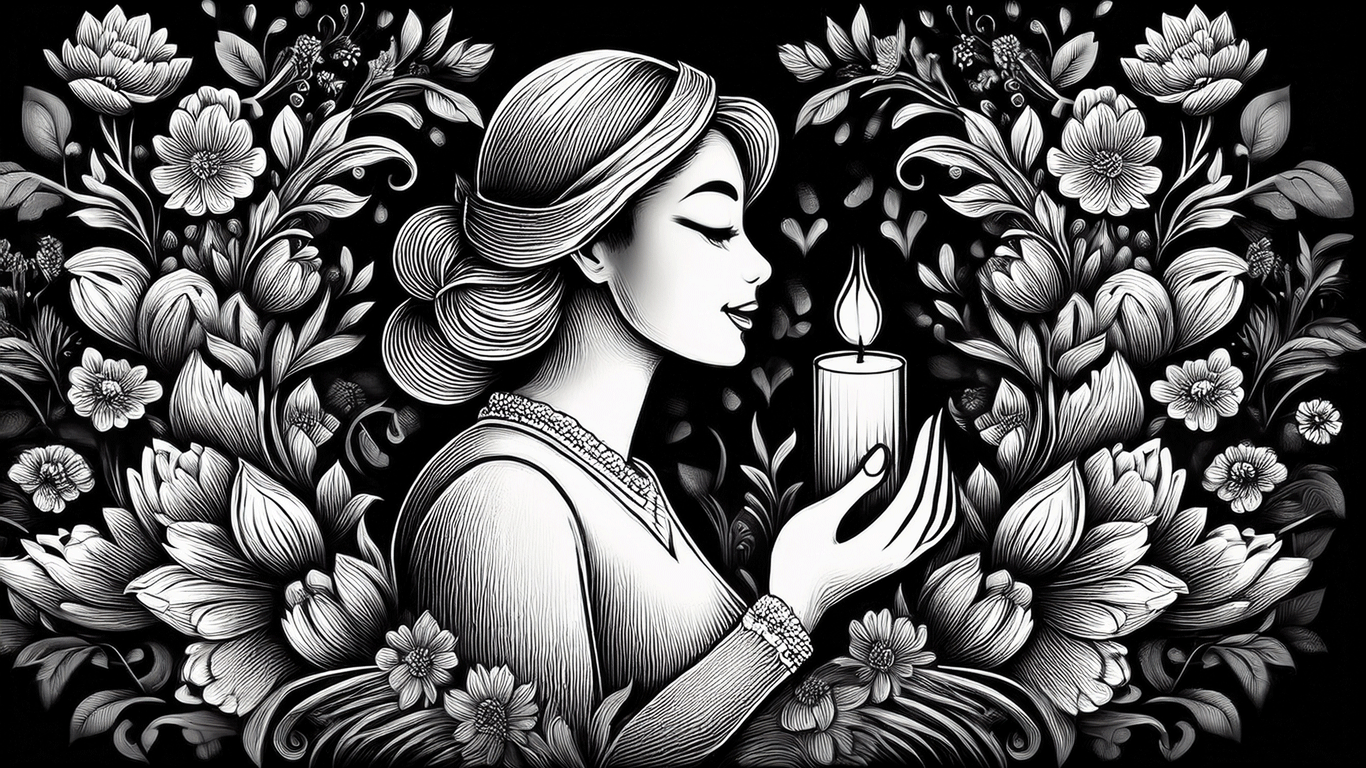
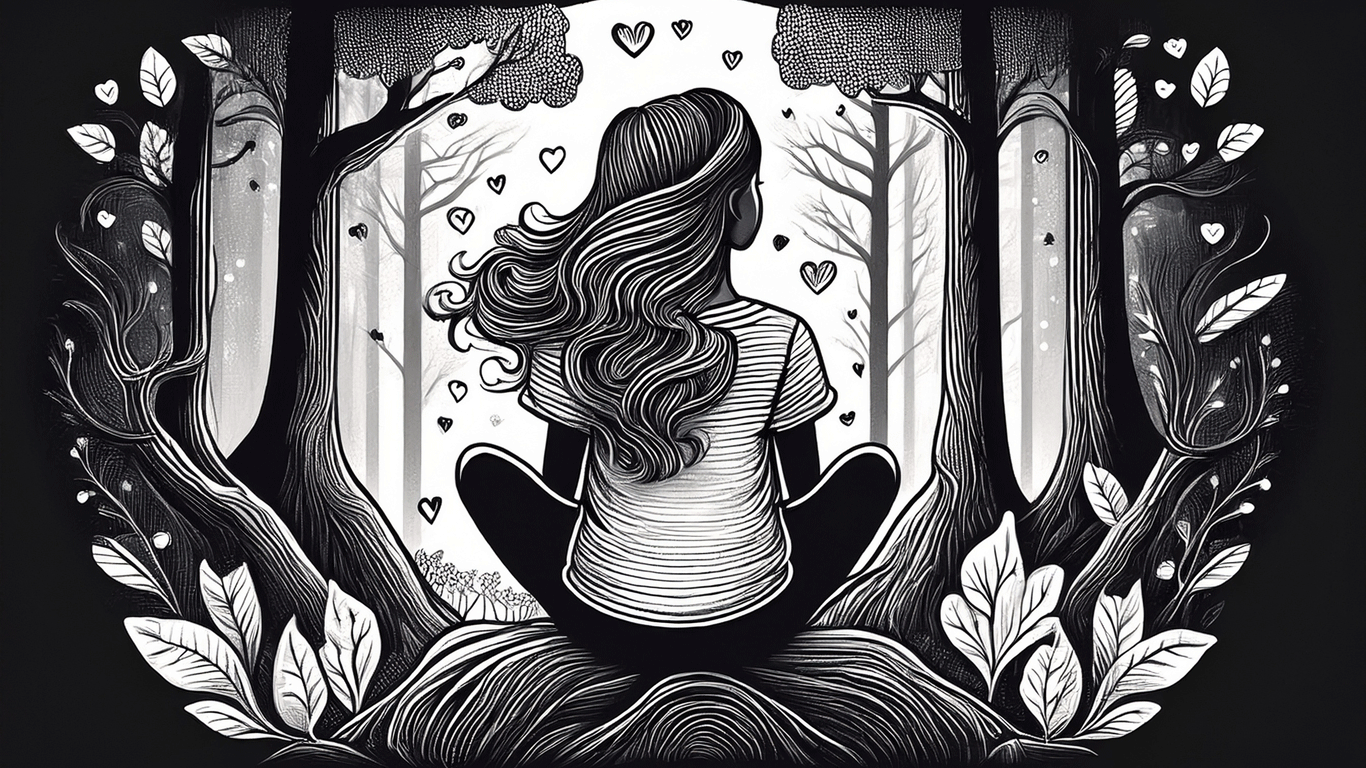
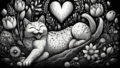

コメント