「認知症の疑いがあります」──医師からの突然の言葉に、不安と混乱で頭が真っ白になる方は少なくありません。
私自身、家族の物盗られ妄想が表面化し、「まさか」という気持ちと「やはり」という予感が入り混じり、大きなショックを受けました。しかし、認知症と向き合うことは、決して終わりではありません。適切な知識と冷静な対応があれば、その後の生活を穏やかに、そして本人らしく送るための道筋が見えてきます。
この記事では、認知症と診断された直後にご家族が「何をすべきか」を明確にするため、すぐに取り組むべき7つの初期対応ステップを具体的にご紹介します。
なぜ初期対応が重要なのか?
認知症の診断は、家族にとって大きな転換点です。この時期に適切な対応をすることで、その後の介護生活の負担を軽減し、何よりも本人と家族の穏やかな毎日につながります。
「何から手をつければいいのかわからない」という方もご安心ください。一つずつ段階を踏んで、できることから始めていきましょう。
認知症と診断されたら家族がすぐにやるべき7つの初期対応
1. 病名を受け入れ、感情を整理する
診断直後は、「まさか」「信じたくない」といった感情が湧き上がって当然です。本人もご家族も大きなショックを受けることでしょう。しかし、現実は今日と同じ明日がやってきます。
無理に感情を抑え込む必要はありません。まずはご自身の気持ちと向き合い、少しずつ病名を受け入れるための時間を持つことが大切です。信頼できる人に話を聞いてもらったり、同じ境遇の方の体験談を読んだりすることも、気持ちの整理に役立つでしょう。
2. 認知症のタイプと進行度を正確に確認する
「認知症」と一口に言っても、その種類は多岐にわたります。
- アルツハイマー型認知症
- レビー小体型認知症
- 前頭側頭型認知症
- 血管性認知症
など、それぞれ症状の出方や進行が異なり、対応方法も変わってきます。
担当医に「どのタイプの認知症なのか」「現在の進行度はどの段階か」を必ず確認しましょう。これにより、今後の見通しが立てやすくなり、適切なケアプランを考える上で重要な情報となります。
3. 信頼できる「かかりつけ医」と専門医との連携体制を築く
認知症は長期的に付き合う病気です。定期的に受診でき、いつでも相談できる「かかりつけ医」を持つことは、ご家族にとって大きな安心感につながります。
もし、かかりつけ医がいない場合は、早めに探すことをお勧めします。また、症状によっては、精神科、神経内科、もの忘れ外来などの専門医との連携が不可欠です。例えば、私の場合は、普段の持病はかかりつけ医に診てもらっていますが、認知症に関しては専門の「もの忘れ外来」に通院しています。
複数の医療機関と連携することで、より包括的なサポートを受けられるようになります。
4. 介護保険の申請手続きをすぐに始める
認知症と診断されたら、速やかに介護保険の申請手続きを始めましょう。これは、介護サービスを利用するために不可欠なステップです。
- 申請窓口: 地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険担当窓口
- 申請代行: ご家族が代理で申請できます。
地域包括支援センターは、認知症の診断が下る前でも相談に乗ってくれます。「もしかして?」と感じる症状がある段階で、勇気を出して相談してみるのも良いでしょう。
申請後には、認定調査や主治医の意見書を経て「要介護度」が決定します。要介護度に応じて、訪問介護やデイサービスなど、様々な介護サービスが利用できるようになります。
5. 本人の意思を尊重し、「できること」に焦点を当て役割を残す
「もう何もできない」と本人に思い込ませてはいけません。認知症と診断されても、本人ができることや好きなことはたくさんあります。
- 家事の手伝い
- 趣味活動
- 得意なこと
など、生活の中に役割を残すように心がけましょう。「できなくなったこと」にばかり目を向けるのではなく、「まだできること」に注目することで、本人の自信や自尊心を保ち、症状の安定にもつながります。
6. 家族内で情報共有と役割分担を徹底する
介護はマラソンと同じで、長期戦になります。ご家族だけで無理なく支え合うためには、情報共有と役割分担が不可欠です。
- 連絡手段: LINEグループやノートアプリなどを活用し、体調変化や気になることなどをこまめに記録・共有しましょう。
- 記録の習慣: 私自身、家族の物盗られ事件をきっかけに「Day One」というアプリで日々の出来事を記録しています。これは、後から状況を振り返る際に非常に役立ちます。
- 役割分担: 特定の家族に負担が集中しないよう、介護の役割を明確に分担し、定期的に見直すことが大切です。
7. 地域包括支援センターに相談する
「どこに相談すればいいか分からない」と迷ったら、まずは地域包括支援センターへ相談しましょう。
地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域で支えるための総合相談窓口です。介護保険申請の流れ、ケアマネジャーの紹介、利用できる制度など、認知症に関するあらゆる相談に丁寧にのってくれます。
私も初めて地域包括支援センターを訪れた時はドキドキしましたが、親身に話を聞いてもらえ、とても心強かったです。
まとめ|「できること」に注目し、本人らしく穏やかに支える
認知症と診断された時、戸惑いや不安は計り知れません。しかし、適切な知識と、利用できるサポート体制を整えることで、本人が**「自分らしく穏やかに」**生活を送ることは可能です。
そして、これは決して他人事ではありません。私にとって、サニーちゃん(ご家族の名前)の姿は、自身の未来を映す鏡のように感じています。
「できないこと」に目を向け、ため息をつくのではなく、「できること」に注目し、それを最大限に活かす。
この視点を持つことで、本人とご家族が共に安心して、充実した生活を築いていけるはずです。一歩ずつ、焦らずに進んでいきましょう。
[読者への問いかけ]
認知症の初期対応について、他に気になることはありますか? もし、あなたが「これはやっておいてよかった!」という経験があれば、ぜひコメントで教えてください。

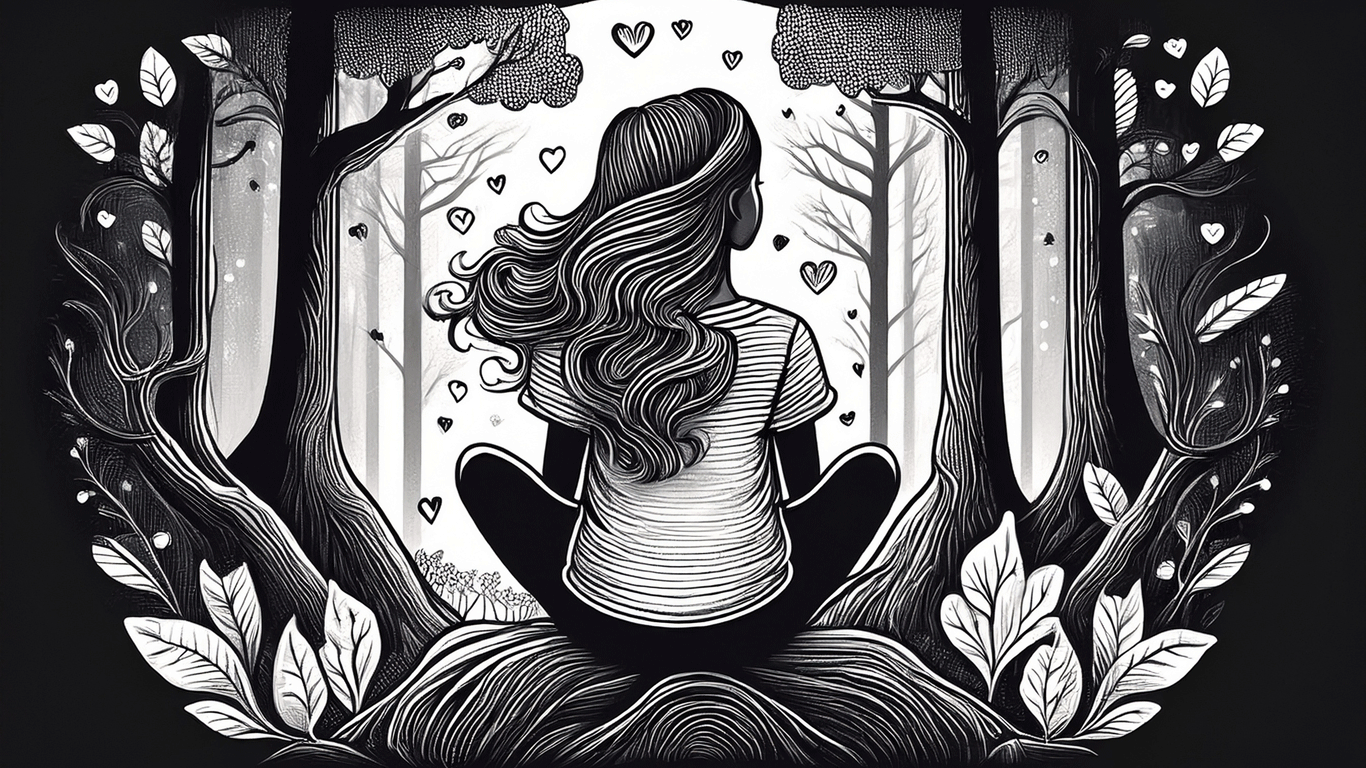


コメント