最近、初めてissue+designさんの認知症ワークショップにオンラインで参加しました。Zoom初心者の私は、慣れない画面に戸惑い、まさに「異世界に迷い込んだ旅人」になった気分。その時、ふと気づいたんです。もしかしたら、認知症を抱える人たちの毎日も、こんな風に不安な気持ちでいっぱいなのかもしれない、と。今回は、私がワークショップで学んだことをご紹介いたします。
学び1:認知症の理解を広める『ファシリテーター』の存在
ワークショップの認知症のことを世の中に広めていく活動をする人「ファシリテーター」についての紹介でした。認知症=何もわからない人という認識が色濃い今日この頃、認知症ファシリテーターのような存在は、認知症についての理解を広めるために大切だと思いました。
学び2:『ダイアログカード』で「当事者の困りごと」を考える
実践編では、ケーススタディ形式で学びました。issue+designさんが作成したダイアログカードをヒントに、当事者の方の困りごとを推察したり、解決方法をグループで話し合ったりするものです。
私にとっては、前提条件がざっくりしていてカードは少し使いづらく感じましたが、当事者の状況を想像し、多様な視点から問題を考える良い訓練になりました。
学び3:すぐに実践できる「暮らしのヒント」
もう一つの課題は、ある寝室のイラストを見て「認知症の方が住みやすくなるには、どこを変更したらいいか」を話し合うというものでした。これは、特に具体的な気づきが多く、とても勉強になりました。
【認知症の方が感じている「お困りごと」】
- 床や壁の色が同じだと、空間や奥行きがわかりにくい。
- 強い光と影のコントラストがあると、影の部分が「穴が空いている」ように見えてしまう。
- タンスや戸棚に扉があると、中身がわからなくなる。
- トイレと他の部屋のドアが似ていると、どちらがトイレかわからなくなる。
- 針だけのアナログ時計は、時間が読み取りにくい。
【私たちができる「暮らしの工夫」】
- 床と壁の色を区別できるよう、壁紙やカーテンの色を変える。
- カーテンなどで部屋の中に強い影が出ないようにする。
- タンスや戸棚の扉を外す。
- トイレのドアをいつも開けておく。
- アナログ時計は、数字がはっきりと書かれたものに変える。
まとめ:ワークショップに参加して、感じたこと
今回のワークショップを通して、認知症の人の世界を少しだけですが、体験できた気がします。そして、何よりも大切なのは「一人で悩まずに、多くの人と話し合うこと」だと強く感じました。自分一人では気づけない視点や解決策を、皆で出し合うことの重要性を学びました。
本当はもっと認知症の人の気持ちの変化や脳の仕組みなど、内面についても深く知りたかったので、また次回ワークショップがあれば、ぜひ参加したいと思っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
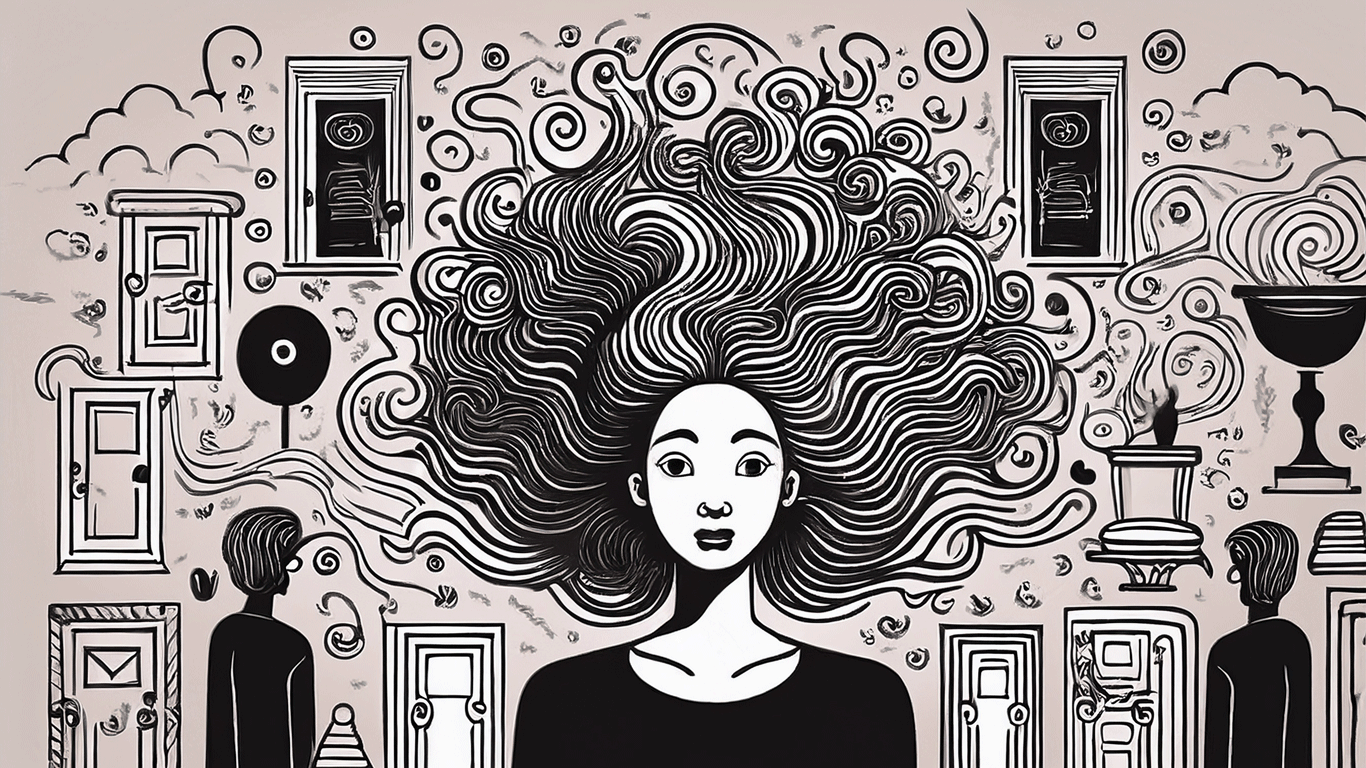
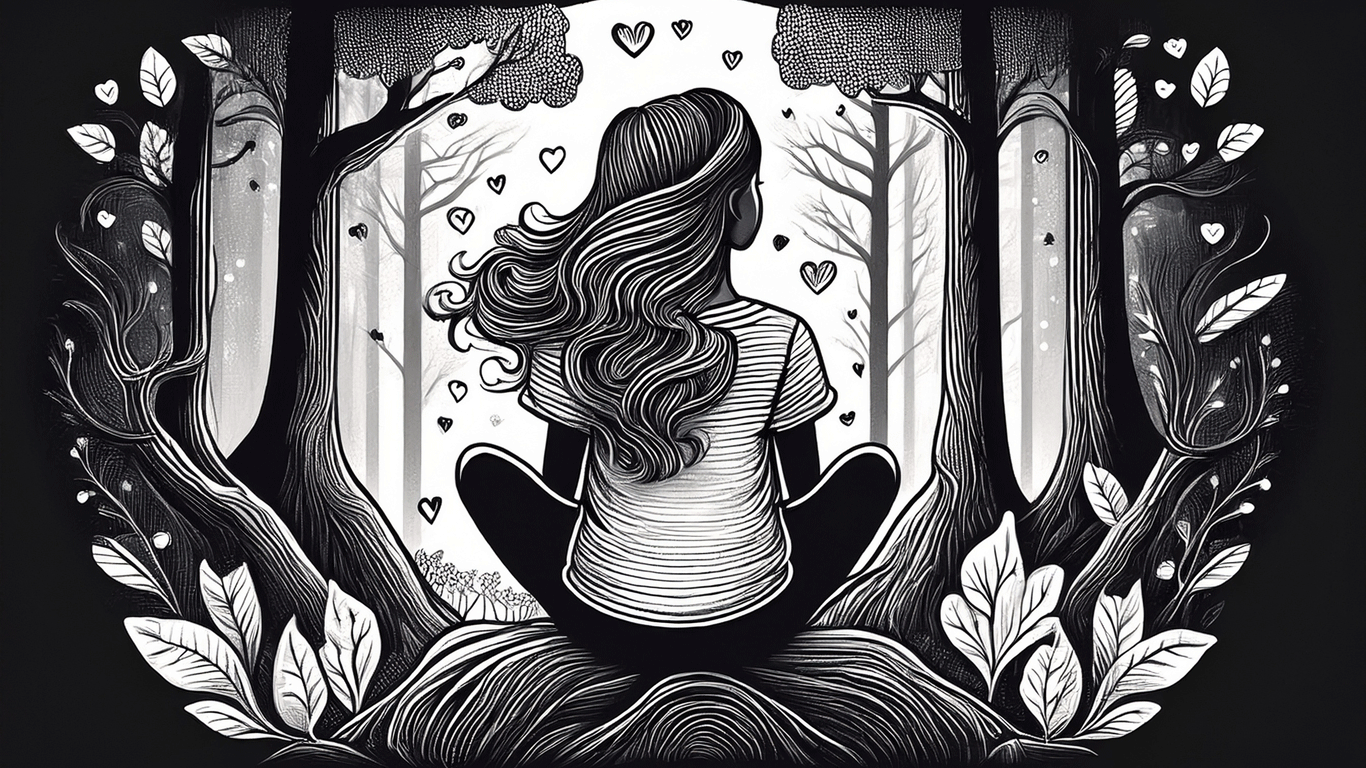


コメント